みなさんこんにちは。
守備が上手い選手と言えばどの選手を想像するでしょうか。
現役選手だと、西武の源田選手、広島の菊池選手、オリックスの安達選手辺りが僕の中ではトップクラスだなと感じます。
過去のプロ野球選手に目を置くと、元ロッテの小坂氏や元ヤクルトの宮本氏が圧倒的な存在感でした。
僕も学生野球時代なんかはこれらの選手にあこがれを持って動画を見たり研究をしていました。
しかし、それでも内野守備においてエラーは付き物です。
どんなにうまい選手でも、絶対にエラーをしないなんてことはありません。
だけど上手い選手は圧倒的に守備率が高く、今ではUZR(Ultimate Zone Rating)などを用いて守備の指標も出されるようになってきました。
「内野を守るようになって打球が怖い」
「どうしてもゴロをエラーしてしまう」
「ゴロはバウンドが合わなくて難しい」
そんな野球人のために、僕が元プロ野球選手に教わったことも交えながら、
内野守備を向上するために何を意識すればよいかまとめました。
内野守備で意識すべき3つのこと
目線の高さについて
まず意識すべきことは「目線の高さ」です。
良く腰を低くしろなどと言われますが、要は目線を下げるということです。
今の目線の高さから15センチくらいは下げる意識でいてください。
なぜ目線を低くするかというと、理由は2つあります。
1つ目はバウンドの高さを見極めることができるから。
2つ目はグローブを下から出すことができるから。
この2つです。
正直なところバウンドが高かったらあまり目線を下げる必要はありません。
どちらかというと目線よりも低いバウンドの打球を処理するときには目線を下げておく必要があります。
目線を下げておかないと、バウンドの高さが見極められずバウンドが合わせられなかったり、グローブを上から出してしまい、打球がグローブの下を抜けていってしまうかもしれません。
目線は一瞬下げればいいという訳ではなく、打者が打った瞬間から低く打球に向かう必要があります。
それは、打球は速いうえに、途中でバウンドが変わるかもしれないからです。
速い打球や途中でバウンドが変わる打球に対しても、常に低い位置で目線を保って打球を追えば、
良い形で捕球することができます。
注意すべきこととしては、目線を下げても腰を浮かせすぎないということ。
逆に腰を低くさせすぎても良くありません。
目線が大事だからと言って、動きが遅くなってしまっては意味がありません。
腰が低くしすぎると動きが遅くなり、高いと目線も浮きやすくなってしまいます。
目線の高さについてまとめ
1.打者が打った瞬間から捕球するときまで常に低い位置で動く
2.素早く動き、ぶれないよう腰は高すぎず低すぎず
3.いつもより15センチくらい目線を下げる意識で!
左足を出す(着く)タイミングについて
次に意識すべきポイントは「左足を出すタイミング」です。
多くの人が小学生のころに、右足→左足→グローブの順番で出すように
指導されたのではないでしょうか。
実際に僕も大学に入るまでは、右足→左足→グローブを意識していました。
しかし、動画が主流となってきた大学入学に阪神鳥谷選手のスロー動画を見て違いに気づきました。
※動画は削除されているようで見つけられませんでした。
プロでも一級の守備を誇る選手はみな、右足→グローブ→左足の順で捕球から送球を行います。
上記は源田選手の試合での動画です。
明らかに意図的に右足→グローブ→左足の順で捕球から送球までしています。
ではなぜ、右足→グローブ→左足の順で守備を行う方が良いのでしょうか。
主な理由は2つあります。
1つ目は、スローイングにキレイな間を作ることができるからです。
右足→左足→グローブの順になってしまうと、どうしても体重が前のめりになります。
そうなると勢いがある場合は特に、ワンステップで投げることができません。
一方で、上の動画のように右足→グローブ→左足の順だと、スローイングまでに間ができます。
この間ができれば、余裕をもってスローイング体勢に入ることができるため、
どのような形で捕球したとしても、ワンステップでスローイングをすることができるのです。
2つ目の理由は、少し前や少し後ろの打球に対応できるからです。
左足が先に着くと、もう捕球体勢を取るしか選択肢が無くなります。
したがって、前に出たかったらもう一回右足→左足とステップしなければなりません。
後ろに下がることにいたっては、重心が前のめりになっているため、そもそもできない可能性が高いでしょう。
一方、右足でためを作って左足がまだ着いていなければ、前の打球であれば大きく一歩を踏み出すことができ、後ろであれば左足を下げればよいだけになります。
捕球まで体勢の基本まとめ
・右足→グローブ→左足の順で着く
→スローイングまでの間を作り、ワンステップで投げれることができる。
→右足でためを作り、前後の打球にも対応できる。
捕球の位置について
最後に意識すべきことは「捕球の位置」です。
結論を言いますと、体の中心から右側で捕球するよう意識してください。
これについては、意識するというよりも自然にそうなってしまいます。
2つ目に書いた、右足→グローブ→左足の順で右足にためができると、左足の前で捕球しづらいです。
右足に体重が乗っているときには捕球態勢に入るので、その姿勢で一番自然な位置にグローブをもっていきましょう。
自然と体の中心から右側によるはずです。
よく、左側で捕球すれば跳ねても体に当てれば後ろに逸れないから左足の前で!という指導者もいますが、これについてはまず左足の前で捕ろうとすると左足がグローブよりも先に着き易くなってしまいます。
また、体に当てても落としたら大体セーフです。(笑)
ということで、プロでも右側で捕る意識でやっていることからも体の左側捕球論はあまりアウトにするという目的に沿わないので、やめておきましょう。
それでは今まで確認した
・目線の高さ
・右足→グローブ→左足の順
・体の右側で捕球
この3つを完全会得するための練習方法をお伝えしましょう。
プロ並みの守備力を得るための練習方法
<STEP1>
5メートル離れた位置から手でボールを転がしてもらい、右足→グローブ→左足のタイミングをひたすら体に叩き込む。
※この時は目線の高さはあまり気にしなくて良い
<STEP2>
10メートルほど距離を取り、目線の高さと足のタイミングを意識しながらゴロを転がしてもらう。
その時のポイントは、
・ボールがどのあたりに来たら右足を着くのかを把握する
・捕球までのリズムをつかむ
<STEP3>
形、リズム、タイミングが取れるようになったら、ポジションについてノックを受ける。
というような流れで練習を行ってください。
慣れないうちはSTEP1に時間をかけましょう。
(僕もSTEP1での右足→グローブ→左足のタイミングを完璧に染み込ませるのに3週間くらいかかりました)
捕球時は必ず体の中心から右側で捕球することを意識して下さい。
さいごに
僕は、体も決して大きくなく中高大とずっと守備キャラでした。
(結構打てると思っているが、守備キャラ感が強すぎるっぽい)
だからこそ、守備の研究には力を入れてきましたし、主にショートを守っている以上高い守備力が求められてきました。
レベルが上がるにつれて、新しく教わることが増え、大学から先でかなり守備は上達したと感じます。
ちなみに今まで述べたことは、プロに入った先輩や独立リーグの練習会に参加したときに元プロ野球選手のコーチに教わり、自分なりに解釈したことを述べています。
実際に独立リーグのトライアウトを受けた時も周りの選手から守備について聞かれたり、球団の方にも他のポジションを守れるかどうかなど、守備について話題になることが多かったです。
今は軟式野球をやっていますが、普通にしていたらエラーすることはほぼ皆無です。
(メジャーを意識しすぎて、弱い打球を素手で捕ろうとしまくりエラーがあります(笑))
今までに述べたことをひたすら反復練習し、体に染みついた結果だと思います。
バウンドが合わなくてやばいと思った時でも体は勝手に反応してくれます。
初心者の方でも、高いレベルでやる方も、ぜひ参考にしてみてください。
それではまた!
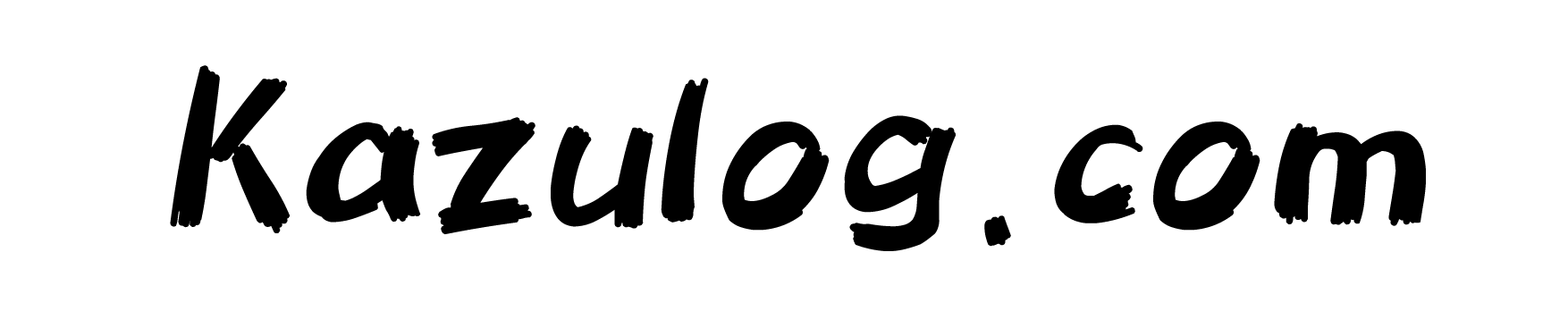

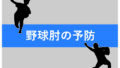
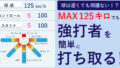
コメント